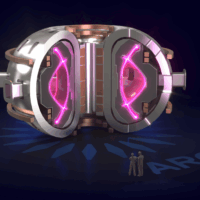2011年3月11日に発生した未曾有の大震災、東日本大震災。日々メディアで伝えられた、とても現実とは思えないような被災地の状況を今でもはっきりと覚えています。あの日から10年が経ち、被災者の今を伝える報道も徐々に減りつつあります。実際に東日本大震災を経験した当時の被災者は、震災前のような「当たり前の日常、日々の生活」を取り戻すことができているのでしょうか。
前回(2020年9月7日掲載)、九州豪雨を例に災害時の避難所について解説した都市計画や災害復興が専門の地域創造学部田中正人教授の再登場です。今回はこの10年間の復興事業で被災者は「震災前の生活を取り戻せているのか」という問題意識の下、復興事業の現状と課題、そして今後の大規模災害への教訓についての解説です。
INDEX
未曾有の被害をもたらした東日本大震災。その被害と特徴は?

(出典:内閣府防災情報のページ http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/63/special_01.html)
建築物に加え、地盤や防御施設にも甚大な被害
(編集部)多くの死者・行方不明者を出した東日本大震災の被害と特徴はどのようなものだったのでしょうか?
(田中先生)2011年3月11日、三陸沖を震源に発生したマグニチュード9の地震(東北地方太平洋沖地震)により、場所によっては波高10メートル、遡上高30メートル以上にもなる巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。12都道府県で1万6,000人近くの死者を出し、発災から10年となる2021年現在においても、未だに2,500人あまりが行方不明となっています。被災地が広域にわたったため、ピーク時には40万人以上が避難生活を余儀なくされました。阪神・淡路大震災を大きく上回る、戦後最悪の被害規模となりました。死者数に加えて行方不明者数の多さ、死者に対する負傷者の少なさ、避難先の広域性が際立っています。
住宅の被害は約12万棟、これは阪神・淡路大震災の時とあまり変わりませんが、東日本大震災では地震・津波により地盤ごと破壊された点、そして本来防御する設備である防潮堤が大きな被害を受けたという点が特徴として挙げられます。地面が残っていれば、その上にまた建物を建てることができますが、東日本大震災では土地そのものが崩壊してしまった。防潮堤も津波を防ぐことができなかった。この2点は、ふたたびどこに住むのかという問題につながりました。
防災・減災に対する考え方にも変化
(編集部)東日本大震災は国民にとっても未曽有の大災害だったわけですが、復興事業に対する考え方にも影響を与えたのでしょうか?
(田中先生)広範囲にわたる地震・津波被害、そして原発事故という複合災害となった東日本大震災は、その圧倒的な物的被害と人的被害から、法体系も含めた今後の防災・減災の考え方を、根本から大きく変えるきっかけとなりました。
当時、「想定外」という言葉がよく使われました。原発事故に関しては確かに(警告を発していた一部の専門家を除き)想定外だったと言えますが、地震・津波については想定はされていた。しかしその想定を遥かに凌ぐハザード(危険)が襲い、あれだけの被害が起きてしまったわけです。この経験をきっかけに、これまでの「自然現象をコントロールし、被害を防ぐ」という方針から、「自然現象を完全にはコントロールできないという前提のもとで、できるだけ被害を減らす」という方針へ、大きく方向転換したのです。
東日本大震災の復興事業とは。潜在する3つの問題点とは。

東日本大震災の復興事業の考え方
(編集部)東日本大震災をきっかけとして復興事業の政策方針は大きく転換したとのことですが、その具体的な取組はどのようなものでしょうか?
(田中先生)自然災害に対する基本的な考え方は転換したものの、実は具体的な取組の根本は変わっていません。「Build Back Better」、つまり元に戻すのではなく「よりよく作り変える」という発想です。「創造的復興」とも呼ばれました。
巨大な防潮堤を再整備しつつ、ふたたび津波が襲ってくるエリアからは撤退し、内陸や高台に新たなまちを造成する、もしくは盛土整備で地盤面を上げる。東日本大震災の復興事業はこの「防潮堤建設」「内陸・高台移転」「災害危険地区指定」「盛土整備」という4つのプログラムの組み合わせで成り立っていると捉えることができます。組み合わせのバリエーションはさまざまですが、既存のまちを大きく作り変えるという点は共通しています。
東日本大震災を経て、私たちはリスクには上限がないこと、自然を人為的には制御し切れないことを認めざるを得ませんでした。復興事業はそこからスタートしたはずでした。ところが、実質的な取組としては、関東大震災以来の、大きくまちを作り変える「Build Back Better」主義が続いていると言ってよいと思います。
復興事業に潜在する3つの問題点
(編集部)「災害復興、都市計画」の観点から、10年間に及ぶ復興事業の問題点や課題にはどのようなものがあると考えていますか?
(田中先生)第1に、なぜここまで大きくまちを作り変えるプロジェクトが被災地全域にわたって実施されることになってしまったのかという問題です。巨大な防潮堤に関しては、必要性や高さの判断をめぐって激しい論争が各地で巻き起こりました。沿岸部を災害危険区域に指定し、居住を禁止したにもかかわらず、その眼前に超ハイスペックな防潮堤が屹立する風景は誰がみてもナンセンスです。
また被災直後に復興構想会議(※1)が高台移転を打ち出したこともあり、多くの自治体が移転を前提にまちづくりを考えることになりました。主に採用されたのは、1972年に制定された「防災集団移転特措法」(※2)に基づく事業です。この法律は本来、山間部や島しょ部の小さな集落が自らの意思で移転と移転先を決め、それを促すことを目的に制定されたものです。しかし東日本大震災では、最初から移転ありきの方針で物事が進みました。集落の主体性、自主性が前提にあるべきなのですが、そこが完全に抜け落ちていました。さらに、「移転先が決まらないまま、居住地が災害危険区域に指定される」という転倒もありました。本来、防災集団移転の前提は、先に移転先を決めてから元住んでいたところを危険区域に指定します。東日本大震災ではここが逆転していたケースも多く、結果としてさまざまな対立や不和、軋轢を生みました。その後、修正や特例が重ねられましたが、結局は構造的な欠陥のもとで、場当たり的に対症療法が繰り出されたにすぎません。
(※1)2011年4月11日、東日本大震災の被災地域の復興に向けた指針策定のための復興構想について、内閣総理大臣の諮問に基づき審議を行うために設置された政策会議。2012年2月10日の復興庁の設置に伴い、東日本大震災復興構想会議は廃止された。
東日本大震災復興構想会議 https://www.cas.go.jp/jp/fukkou/
復興庁 https://www.reconstruction.go.jp/
(※2)「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」の略称。大規模な自然災害などが発生した地域や建築基準法で規定された災害危険区域にある住居の集団移転を促進するために、地方公共団体が行う事業にかかる経費の大半を国が負担することなどを定めた法律。1972年制定。
第2に、長い時間がかかる大規模な事業は、被災者の一日も早い生活再建とはそもそも相容れないのではないかという問題です。復興事業の4つの取組は、どんな組み合わせで実施するにしても、完成するまでに5年、10年、場合によってはさらに長い期間を要します。その間、被災者はもともと住んでいた土地を離れざるを得ない。つまり、被災者にとっては「原住地との関係が途切れること」、そして「長く不安定な仮住まい状態が続くこと」を意味します。これこそが、その後の復興過程において起こる様々な問題――自力再建の断念や生業再開の困難、経済的困窮、災害関連死、社会的孤立や孤独死――の根底にあると考えています。
東日本大震災の被災地は、第一次産業に従事する被災者も多く、仕事と住む場所が分かち難く重なり合っていました。原住地からの隔離は、住宅の再建だけでなく生業の再建にも困難を強いることになりました。また多くの高齢者にとっては、近所の住民からの援助やかかりつけの医者など、地域で築いてきた関係を取り戻せない期間が長く続いていくことになったのです。
第3に、復興事業はまちを大きく作り変える一方で、変えずに残すべきものを余りにもないがしろにしてきたのではないかという問題です。「Build Back Better」主義に基づく復興は、たしかに災害に対する安全性を高めます。しかし土地に根ざし、地域と密接な関係を築いてきた人びとにとって、それは復興とは逆行する、生活再建の手がかりを失うことにほかなりません。たしかに地盤被害の大きさは、元の場所での生活の再開を難しくしていたかもしれません。ですが重要なことは、その場所には過去に積み重ねられてきた無数の生活の蓄積があるということです。第三者がすぐに感じとるのは難しいのだと思いますが、たとえ何もかも流され、破壊されていたとしても、そこには暮らしを立て直す手がかりがあったはずです。それを保護するという発想は、東日本大震災の復興事業にはほとんどなかったと言えるでしょう。
一方で、注目される事例もありました。例えば、岩手県釜石市花露辺地区は14.5メートルの津波に襲われ、約70世帯のうち25世帯の家屋が流失するという厳しい状況にありましたが、早い段階で住民合意のもと集団移転の計画をまとめ、生業である漁業と住宅の再建を早期に実現させています。
東日本大震災から考える「来たる未来の災害」に備えて

東日本大震災からの教訓。被災地に「何をつくるか」ではなく「何を残すのか」
(編集部)西日本一帯に甚大な被害をもたらすとされる南海トラフ巨大地震も予測されていますが、東日本大震災の教訓から復興を考える上で大切なこととはなんでしょうか?
(田中先生)今後30年以内に70~80%の確率で発生すると予測される南海トラフ地震ですが、東日本大震災のあとに、大幅な想定被害の見直しがなされました。巨大な津波が早ければ2~3分後に到達し、犠牲者は最大約32万人に及ぶ。この衝撃的な数字は、行政だけでなく住民にも直接的な影響をもたらし、沿岸地域からの自主的な移転を促しています。南海トラフ特措法や津波防災地域づくり法は、いわばこの動きを後押しするものです。実際、太平洋沿岸自治体の庁舎や病院、保育所などが高台に移転し、若者向け公営住宅などが整備されています。つまり、被災後の復興ではなく、今のうちに「事前復興」を進めようという政策です。こうした取組によって、想定される犠牲者の数は2020年には23万人にまで減少しました。
また昨年は、都市計画法・都市再生特措法が改正され、防災と都市計画の連携が図られることになりました。人口減少が本格化し、いま都市計画の中核にあるのは「徐々に人が住む場所を集約していく」というコンパクトシティ(※3)政策です。一方、防災・減災政策は、制御不能なハザードからは撤退するという発想のもと、居住を制限する危険区域や警戒区域の指定を拡大しています。両者を重ねることで、よりリスクの少ないエリアに人を誘導しつつ市街地のコンパクト化を図るという考え方です。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001326007.pdf
以上の2つの政策動向は、いずれもきわめて合理的に思えます。ですが、実際はそんなに単純ではありません。まず「事前復興」の推進に関しては、確かに全体的には良い方向に向かっているように思えますが、高台に移転可能な世帯は限られます。沿岸部には危険な状態で取り残されている人がいます。つまり、安全な高台には豊かな人びとが移転し、沿岸部には弱者が取り残されるというコミュニティの分断が起きています。また「コンパクトシティ」の推進に関しても、将来を見据えれば避けて通れない道のりであると思われますが、前述のように、居住地の移転は土地に根ざしてきた人びとにとってはそれ自体がリスキーです。原住地との関係の途絶は、日常を破たんさせることになりかねません。津波のリスクを避けるために、日常が破たんしてもやむを得ないとは到底思えません。
これらはまるで、東日本大震災の問題が、西日本太平洋沿岸部へと場所を変えて再現されているように思えてなりません。特定のハザード(危険)を絶対的なリスクとみなし、造成と移転によってまちを大きく作り変えるという「Build Back Better」主義が人びとの自律的な生活を損う――、これこそが東日本大震災から私たちが学ぶべき最大の教訓であると思います。
とはいえ、差し迫った自然災害のリスクを前に静観しているわけにはいきません。避けうるべきハザードは避けられなければならないでしょう。参照すべき一例として、奈良県十津川村の集落再編のプロジェクトがあります。2011年の紀伊半島大水害により甚大な被害を受けた村では、原住地との関係を保ちながら段階的に危険な区域からの移動を誘導する事業が進んでいます。時間はかかっても、元の生活環境の一部を変えずに、ゆるやかにリスクを減らすという点に、重要な示唆があると思っています。
これまでの復興政策は「被災地をいかに作り変えるか」にひたすら注力する「Build Back Better」の思想が前提にありました。被災地での日常を一日も早く取り戻すためには「何を作るのか」ではなく、その地域で長年培われてきた生活に向き合い「何を残すのか」を考えることが求められるのではないでしょうか。
まとめ
被災地の復興において重要なことは、被災者の「日常の連続」を断ち切らないこと。被災地の瓦礫が撤去され、道路や住宅がきれいに整備されたとしても、被災者のそれまでの日常が戻らない限り、それは本当の意味での「復興」になりません。「何をつくるか」ではなく「何を残すか」。地域のコミュニティ、仕事、住宅・・・。残すものが何かによってつくるものも変わります。そしてそれを決めるのは住民間の合意と普段からの防災意識ではないかと思いました。
近い将来、必ず発生すると言われている南海トラフ巨大地震では西日本一帯が甚大な被害を受けます。復興とは誰のためのものなのか、それは住民であり被災するかもしれない私たちひとり一人が普段から考えなければならない課題ではないでしょうか。