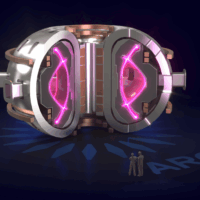医療が大きく進歩した現代、人生の最終段階をどのように過ごすかを検討することは、すでに身近な話題のひとつになってきました。 確実な死期が迫る中で苦痛にあえいでいる場合や、植物状態で回復の見込みなしと診断された場合など、患者側が「過剰な医療を受けず、自然に最期を迎えたい」と願うのも考えの一つかもしれません。 しかしながら現在の日本では、仮に患者本人が真摯に死を望んでいても、医師が死期を早める措置をとる尊厳死・安楽死は合法化されていません。
最近では、難病のALS患者に依頼され薬物を投与して死に至らしめたとして「嘱託殺人」の罪に問われる医師らの事件公判も続いています。(※) 法は本来、私たち社会のあるべき姿を規定するものですが、必ずしも冷静ではいられない人生の最期について法はどこまで踏み込むことができるのでしょうか? 今回は法哲学者の法学部 服部高宏教授と尊厳死・安楽死をめぐる日本の今を考えます。
INDEX
私たちの社会のものさしである“法”と、人がつながる“ケア”

さまざまなアプローチで「あるべき法」を探る法哲学
(編集部)服部先生は法哲学が専門で、看護・福祉領域の「ケア」を研究対象の一つにしていますね。法とケアの関わりについて、どのような点に興味をひかれたのですか?
(服部先生)法哲学とは、法に関して基礎的研究を行う基礎法学の一分野です。種々の課題がありますが、法と法に関わる価値・理念についても、倫理学や哲学、政治学などを交えながら明らかにしていきます。他の分野の法学とは異なり、現にある法自体を疑ったり、理想の「あるべき法」を探ったりすることも許される学問分野です。 法とケアの関わりに興味を持ったきっかけは20年以上前、岡山大学に在籍していた時です。社会人大学院生として研究する看護教員や看護師、福祉専門職の方々を指導したことがありました。 その時に、ケア領域のさまざまな課題を法の枠組みにのせることの難しさと、その難しさゆえに実は、ケアは法があまり対応できていなかった分野であると気づき、以来、法とケアの在り方に関心を持っています。
法の限界?「法」で規定できない「ケア」とは
(編集部)法がケアを考えてこなかった、とはどういう意味でしょうか?
(服部先生)法がその運用において正義を実現するには、既存のルールを厳格に適用していく必要があります。その中では個別の事情は、法律の枠組みの中で考慮されるにすぎず、大きな制約があります。それに法が基本とする正義の考え方の根底には、“自立した個人”の存在があり、「あの人は○○で気の毒だから優遇しよう」と思っても、法の仕組みは基本的にそれを許さないんです。
一方、ケアの現場や考え方では、個別の事情にこそ寄り添うべき大切な一面があります。法で一律に規定できない人と人の情緒的なつながりがあって、他人への思いやりを重視する。助け・助けられ、依存し・依存されるといった関係を含むのがケアです。
このように、ケアの考え方と法の理念には相容れない面があり、そのため、法の考え方や仕組みで看護・福祉の諸問題をとらえるのは難しい面があって、制度化もそれ特有の困難を伴ってきた。でも「ケアの領域に向けて、法にはもっとできることがあるんじゃないか」ということで、ケアの制度化における諸問題について研究してきたというわけです。
法的視点から考える終末期医療

尊厳死と安楽死の違い
(編集部)医療における法といえば、たびたび問題になってきたのが「終末期の現場における尊厳死・安楽死」ですね。
(服部先生)医療の発展で、死に瀕するような重篤な症状の患者でも回復できるようになった反面、本人の意に必ずしも沿わないであろう延命措置も可能になりました。 尊厳死・安楽死をめぐる議論の中で喫緊の課題となっているのが、この終末期の延命措置にあたる治療行為をどうするかです。超高齢化社会に向かう今、ますます身近な問題になりつつあるといえるでしょう。
(編集部)ここで一度、尊厳死と安楽死について一般的な解釈をお聞きしたいと思います。
(服部先生)「尊厳死」は、患者が自身の意思で延命措置を受けることなく、自然の経過にしたがって死を受け入れることを指します。植物状態や終末期の患者に積極的な治療を行わないこと、または延命措置の差し控えや中止をもって、患者が尊厳ある最期を迎えるということです。 「安楽死」は、回復の見込みがない末期患者が激しく苦しむとき、その苦痛を回避するため死期に影響するような措置を施すなど、意図的な手段をもって死を迎えさせることを指します。 後ほど紹介しますが、海外では安楽死の制度化を進めてきた国々もあります。
(編集部)尊厳死や安楽死について、日本ではこれまでどのような議論がなされてきたのでしょうか?
(服部先生)これまで日本の裁判でいわゆる「安楽死」が論じられる場合、3つの種類に分けて考えられてきました。すなわち、回復不能な患者に対し、 ①治療行為を中止すること ②死を早める可能性があると分かりながら苦痛を除去・緩和する措置をとる方法 ③薬物注射など意図的に死を招く方法 です。このうち「①治療行為の中止」は、尊厳死とほぼイコールと考えられます。法の観点から終末期医療の在り方を考えるとき、日常的に論じられるのも①の種類が中心です。「消極的安楽死」と呼ばれることもありますが、その語感ゆえに、この呼び名は誤解を招きやすいかもしれません。 一方、「積極的安楽死」とも呼ばれる典型的な安楽死が③に該当するケースで、日本ではほとんどの場合、殺人罪に当たると言えるでしょう。医師のほか患者家族が関わることも多いです。 ②については、これに相当することは、本人の意思確認など要件を満たせば緩和ケア領域等で行われることもあり、そのこと自体が問題化することはほとんどありません。これも「間接的安楽死」と呼ばれることがありますが、あえて安楽死の部類に入れる必要はないでしょう。
(編集部)広い意味での安楽死をそのように3つに分ける考え方はどこからきたのでしょうか。
(服部先生)広義の「安楽死」をどのように分類・整理するかについては他にも考え方はありますが、ここでご紹介した区別の由来は、1991年に起きた「東海大学病院安楽死事件」の判決文です。事件は、医師が末期がん患者に対し、楽にしてやってほしいとの家族からの強い求めで治療を中止し(①)、それでも苦しそうなので死期を早めることを知りつつ苦痛緩和の処置をし(②)、最後に有害な薬剤を注射し死亡させたというもので、最後の行為が③にあたります。この最後の行為について殺人罪で起訴された医師は、横浜地裁で有罪判決を受け、判決はこの一審で確定しました。 この裁判は、司法が安楽死について丁寧に述べたことで注目を集めました。①~③それぞれで「どういった場合に正当化されるのか」を解き明かしている点でも意義深く、現在の安楽死を考える上でベースになっています。
医療の現場でルール化が求められてきた治療行為の中止とは?
(編集部)すると、広い意味での安楽死に関する今日の中心的な論点は「治療行為の中止」ということですが、実際どういったことが問題になっていたのですか?
(服部先生)医師の視点で考えると、たとえば「延命医療中の患者の体からチューブを抜くと、殺人罪になるのでは?」という問題があります。延命措置をしないことが患者さんの真摯な希望だとしても、行動指針になるルールがないと責任を問われる可能性があり、それに応えられない。そういったことが問題になっていました。 現場の声に応える形で終末期医療に関するガイドラインの策定が進んだのは、2000年代中頃からです。
終末期医療におけるガイドライン策定と、人々の意識の変化

医療現場で望まれたガイドライン
(編集部)ガイドラインが登場したのには、何かきっかけがあったのでしょうか?
(服部先生)2004年から2007年にかけて、終末期患者の延命治療中止の是非を問うニュースが立て続けに日本を駆け巡りました。いずれも患者の呼吸器取り外しが問題になったもので、世間の大きな関心を集めました。延命治療の中止判断が医師にのみ委ねられている現状に鑑み、医療現場からもルール化を求める声が大きくなったのです。
(編集部)ルールが整備されていないことは、医師や医療機関にとって脅威だったんですね。
(服部先生)実際、患者やその家族から治療中止を望まれることもあるようです。医師らはギリギリのところで仕事をしている状態だったのでしょう。 ルール整備の1つの方法として、いわゆる尊厳死法の制定を望む声がありました。しかしそのムーブメントは広がらず、その一方で、様々な医学系学会でガイドライン策定が進むことになりました。医師にとっては学会が示した行動指針という拠り所ができたのですが、まだ十分ではないということで、政府もこの課題に取り組み始めました。 そして2007年5月、厚生労働省からの初のガイドライン「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が発表され、その後幾度となく改訂されてきました。
性急な「法制化は不要かも?」法哲学者の考え
(編集部)結局、日本では法整備ではなく、ガイドラインの策定が進んできたのですね。
(服部先生)国会では超党派議員による「終末期における本人意思尊重を考える議員連盟」が活動しており、法整備を進めようという具体的な動きもありました。しかし、私の見解としては、性急な法整備を進めるよりも、現状ではガイドラインで十分ではないかと考えているところです。
(編集部)法学者である服部先生が、治療中止に関する法は不要だと考えているということですか?
(服部先生)私自身がケアとの関係で法の限界を感じてきたからかもしれませんが、「立法という形での法の介入が、常に物事を良い方向に導くとは限らない」ということには留意する必要があります。 たしかに、ガイドラインには法的効力はなく、それに従えば刑事責任や民事責任を問われないというものではありません。とはいえ、ガイドラインができてから、延命治療の中止に関して医師が刑事責任を問われるケースがほぼなくなったと言われており、実際その傾向はみられます。 現状、ガイドラインが健全な終末期医療のベースを支えているなら、あえて立法による介入をしなくてもよいと考えますし、むしろ医師の免責に重きを置く治療中止に関する法律ができると、その要件を満たしているかどうかに注意が向き、患者のケアの在り方に影響するのではないかと懸念する声もあります。
(編集部)厚生労働省が策定したガイドラインの最新版は、2018年3月改訂の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」ですね。
(服部先生)初のガイドラインから種々の改訂を経る中で、「ケア」という概念が採り入れられ、「終末期医療」が「人生の最終段階における医療・ケア」という表現に変わるなど、より受け入れられやすい形になってきています。 また最新版では、海外発祥のアドバンス・ケア・プランニング(ACP)という考え方が加わり、終末期医療における本人の意思を最大限に尊重すべく事前準備まで言及されている。こういうケースでは医師はこう行動すればよいといった「結論」よりも、患者を中心とした話し合いの方法など「プロセス」を重視しているのが印象的です。
終活とリビング・ウィル。尊重されるべき本人の意思決定
(編集部)最近では「尊厳死」という言葉が世間で認知され、人生の終わりを見越して「エンディングノート」を準備する人、「終活」をする人が増えたように感じます。
(服部先生)その点で言えば、尊厳死にまつわる動きとして、先ほども少しお話しした「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」という事前ケア計画の取り組みは注目すべきものです。日本では今、厚生労働省を中心に「人生会議」という愛称で認知度を高め、普及を進めようとしています。 ACP=人生会議とは、将来の医療やケアについて、患者を主体に家族や親しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、患者の意思決定を支援するプロセスのことです。患者の意思が確認できなくなった時にも、議論・計画をもとに推測することができるとされています。 関西の府県だと大阪府、京都府、和歌山県が活発に普及啓発に取り組んでいますし、市町村でも推進しているところがありますよ。
(編集部)自分が望む形を明らかにしておくことは、周囲の人のためにもなりそうです。
(服部先生)最近では、病気のあるなしにかかわらず、終末期医療に向けた意思を表明する方法として「リビング・ウィル」という書面もあります。書き方は基本的に自由ですが、独自フォーマットを提供している自治体や病院もあって、中には公正証書として作成する人もいます。 注意点として、リビング・ウィルは海外では法的拘束力を持つ国も多いのですが、日本では法的な効力はありません。しかし「本人の意思を探る上で尊重すべき重要な資料」として扱われることは確かです。
(編集部)人生会議にしろリビング・ウィルにしろ、終末期で本人の意思を尊重しようという風向きができてきたんですね。
(服部先生)人生の終わりは、年齢にかかわらずいつ訪れるか分かりません。本当は病気の有無にかかわらず、家族や身近な人と話し合っておくことが大切です。
終末期医療における患者の自己決定。諸外国における制度化のかたち

議論が進んできたポイントは「本人の自己決定」
(編集部)先ほど、海外には安楽死の制度化がなされた国があるとのことでした。注目の国をいくつか教えてください。
(服部先生)立法により積極的安楽死を認めている国としては、オランダやベルギーがよく知られていますが、その他に、ルクセンブルク、カナダ、オーストラリア全州、さらに近年合法化された国として、スペイン、ニュージーランドなどが挙げられます。また、一定条件下で医師による自殺幇助が合法とされる国もあり、立法によるもの、裁判所の判決によるもの、法解釈によるものなど形態は様々ですが、オーストラリア全州、カナダなどのほか、スイスがよく知られています。 立法によるもの以外も含め、本人意思による延命治療の中止が許容されているとみられる国は、アフリカ諸国・アジア諸国などを除き、世界にかなり拡がっています。身近なところでは韓国で2016年に延命医療決定法が制定されました。終末期患者の延命治療について、中止を含み、本人の自己決定を最大限尊重することを目的に制度化されたものです。この法律にのっとって多くの方が亡くなっていることは日本でも報道されたので、関心を持たれている方は多いでしょう。 それぞれに政治的事情や宗教的背景などもあり、これらの国々が法整備に至った背景について一言で説明するのは難しいですが、ただ、終末期医療に関する議論や法整備が進む国々で重要視されている共通ポイントとして「本人の自己決定」があります。
(編集部)本人の意思を尊重するということですね。
(服部先生)とくに欧州諸国がそうでしょうね。積極的安楽死が法制度化されているオランダやベルギーは、患者の自己決定とそれを支える医療システムが根付いていない限り到底実現できるものではないと思います。ナチスの安楽死政策の過去を抱え、安楽死に対する慎重な姿勢を崩さないドイツでも、10年ほど前に「患者の権利法」と題する民法等改正が行われ、患者の事前指示など患者の自己決定の尊重が強固に法制度化されました。 またアメリカは、近年は政治的対立の激化の影響を受けて議論状況が大きく変わってきましたが、もともといろんな地域にルーツを持つ人々が集まる国で、共通の規範というものが見出しにくいことから、「本人がどう思うか」を決定の拠り所とするしかない面がありました。2000年までに全州で、本人の意思決定能力が失われたときに備える持続的代理権や、延命指示書に法的拘束力を与える法律が制定されたほか、2016年にはACPによる患者との相談が診療報酬の対象になり、盛んに実施されています。
(編集部)日本ではまだ感覚として遠い話ですが、法律によって本人の意向が守れられるというのは安心できますね。
「個人の死」のとらえ方、日本と外国では異なる?
(編集部)終末期医療に関するガイドラインが機能する以前、どうして日本では安楽死や延命治療に関するルール作りが積極的になされてこなかったのでしょうか?
(服部先生)安楽死について、日本では法律で規定されない代わりに、裁判において丁寧に対応されてきました。立法による対応はなされていませんが、法によって比較的きちんと扱われてきた問題領域だと思います。しかし、終末期医療を含め、いわゆる生命倫理に関係する事柄について、日本では一般的に、立法による解決を図ることに後ろ向きの傾向が見られます。 その原因を一言で語るのは難しいですが、人の生死にかかわる生命倫理の問題は、個人的な事柄であると同時に家族の在り方にも関わっており、そのことが立法による規律を阻んでいるのではないかと、私個人としては考えています。
生命倫理に関する事柄について、諸外国で「本人の自己決定」が重要視される背景には、それが極めて個人的な事象であり、本人の意思に任せるのが当然だという共通認識があるように思われます。他方、日本の場合、家族と個人を切り離さない独特の規範があると感じます。 その典型は生殖医療に関する事柄で、2020年に生殖補助医療法が成立しましたが、重要な事項について依然として規律がない状況が続いています。親子関係に影響が及ぶことだけに、規律の在り方について合意が成立しづらいのでしょう。本人意思の尊重を基本原則の一つとする臓器移植法に関しても、家族・遺族の位置づけは高く、2009年改正によりその傾向は一層強くなりました。やや性格の異なる法律ですが、献体法でも、家族の承諾に決定的な意義が認められています。
こういった規範が死や終末期ケアにおいても働き、いざというとき本人の意向だけで物事が進まない。死が人間関係の中で起こる出来事になっているがゆえに、法整備やルール作りを遠ざけていた可能性があります。
誰にでも訪れる「死」を、一人ひとりが考えること
(編集部)尊厳死や終末期医療における本人の自己決定をどこまで尊重するか、日本と海外との違いを服部先生はどのように見ていますか?
(服部先生)本人の意思は尊重されるべきで、これに異を唱える人はいないでしょう。ただ、自己決定にどこまでの力を持たせるか。日本と海外で異なるといっても、海外をお手本にすればよいかというと、それは違うと考えます。 真の自己決定のためにはそれを可能にする社会条件が整っていることが前提となります。日本の現在の社会的・文化的状況がそれを可能にするといえるかどうか。ガイドラインを強化するにしても、法整備を進めるにしても、日本の現状に合わせた展開を着実に探っていくことが必要でしょう。
ケアの本質とは、その人自身をかけがえのない存在として固有に尊重することだと考えます。法が「一律の規定を厳格に適用していく」という性質ゆえに、ケアの在り方を窮屈に囲い込むような形になる事態は避けねばなりません。 終末期医療の在り方を法制化するとすれば、理想は「一人ひとりの人生の最終段階におけるより良い生き方を支援できるような法」でしょう。そういった仕組みづくりを研究で模索していきたいと思います。
まとめ
法学者は法による規律を重視するものだと思っていましたので、服部先生が「現状の終末期医療の現場に法律の介入は不要である」と考えていることに、少々驚きました。ですがお話を振り返ってみると、医療や介護など人と人の関わりが深いケアの現場には、個人の感情が介在するだけに、法律で一律に規定すれば万事解決とはならないという難しさがあるいうことなのですね。法は社会秩序を守るために私たちの生活を規定する基準となるものですが、どう適用するかを考えるだけなく、なぜ必要なのかといった背景まで理解することが、社会の未来を考えることにもつながっていると実感しました。
世界一の長寿国である日本にとって、終末期医療の環境を整えていくことは喫緊の課題と言えるでしょう。その環境整備には、医療現場だけでなく、人生会議やリビング・ウィルなど私たち自身による準備も必須のようです。人生最期の瞬間は、きわめて個人的なものでありながら、多くの人に支えられる時間でもあります。一人ひとりが自分なりに考えを進めることが大切なのだと感じました。
【関連記事】