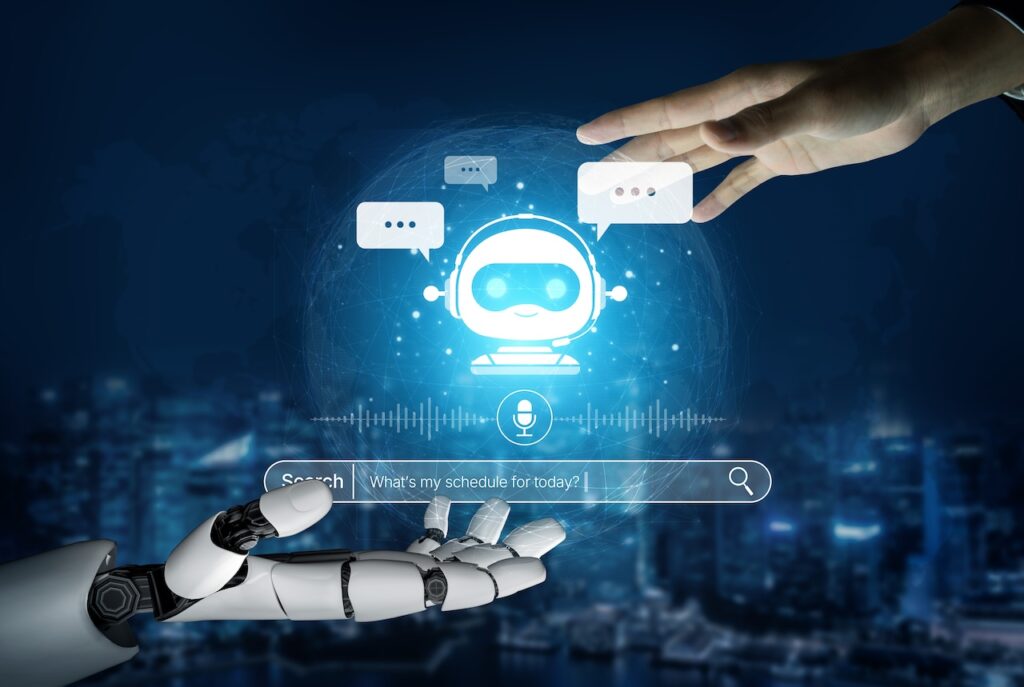近年、OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Gemini」など、大規模言語モデルを活用した生成AIツールが広く普及しはじめています。また、音声認識技術を用いたAIアシスタントの「Siri」や「Alexa」を日常で活用している方も多いのではないでしょうか。 これらAI技術は、まだまだ情報の信ぴょう性といった課題があるものの、文章作成やコード生成、情報収集の支援などさまざまな用途で活用され進化を続けています。最近では生成AIを“日常会話の相手”や“個人的な相談役”として利用する人も増えつつあるとか。
これまで「機械は人間の命令に従って動くもの」というイメージが一般的でしたが、いまや「寄り添い、対話する存在」としてのAI・ロボットが求められる時代へと移りつつあるのかもしれません。 では、ロボットと人は相思相愛の存在になることができるのでしょうか? 今回は、認知科学や心理学の視点から人間とロボットの新たな関係性を模索すべく研究を進め、近著に『人に優しいロボットのデザイン 「なんもしない」の心の科学』(福村出版、2022年9月)がある高橋英之准教授に聞いてみました。
INDEX
コミュニケーションロボットの登場・変遷と関係性の変化

AIを搭載した「aibo」「Pepper」「LOVOT」が私たちにもたらしたもの
(編集部)高橋先生は、人間とロボットとの新たな関係性を探る研究に取り組まれています。まずは、これまでに登場してきたコミュニケーションロボットの変遷について教えてください。
(高橋先生)「コミュニケーションロボット」とは、人と言葉を交わしたり、動作を通じて関係を築いたりすることを目的に開発されたロボットのことを指します。いかにもロボットらしい見た目のものから、動物の姿を模した愛らしいデザイン、小型で携帯可能なタイプまで実に多種多様。 これまでに発表されてきた中では、顔や空間を学習して成長するペット型ロボット「aibo(アイボ)」(1999年~)、感情を認識して対話する「Pepper(ペッパー)」(2014年~)、そして人に懐く家族型ロボット「LOVOT(ラボット)」(2019年~)などが有名ですね。
(編集部)中でもGROOVE X株式会社が開発したLOVOTは、販売開始からおよそ5年で出荷台数が1万4000台を超えるなど人気が高まっています。
(高橋先生)LOVOTは、まるで生き物のように抱っこをねだったり、じっと見つめてきたりする“ふるまい”が特徴的ですね。実証実験のデータによると「LOVOTと暮らす人はオキシトシン(愛着や信頼に関わるホルモン)の分泌が高い」「15分のふれあいでストレスが低下する」といった結果も報告されています。
ひと昔前までは性能面の制約もあり、人がロボットと一緒に暮らすのはなかなか難しい時代でした。一部の熱心なロボットのユーザーがロボットの言動に“積極的に意味づけ”をして、想像力で補っていたところも大きかったと思います。 ですが、この4~5年でAI技術が大きく進化したことで、LOVOTのように「一緒に暮らす」ロボットが実現しはじめています。この進化によって、これまでロボットに興味を持たなかった層にも届くようになり、インタラクティブ(双方向)な関係が築けるロボットの時代が始まったと感じます。
外見に縛られない存在が、人とロボットの新しい関係を生む
(編集部)「双方向のやり取り」ができるようになってきた今、ロボットの外観や設計にも変化が見られるようですが、そういった要素も新たな関係をつくり出すタネになっているのでしょうか?
(高橋先生)LOVOTの設計で興味深いのは、特定の動物や生物をモデルにしていない点です。私たち人間は無意識のうちに、犬型のロボットには犬らしさを、猫型のロボットには猫らしい反応を期待してしまいますが、これは人間が過去の経験や知識をもとに他者と接する生き物だからです。 ですがLOVOTにはそうした“前提”が存在しません。だからこそ、私たち人間はその存在と向き合うために、自分自身で考えて関わる必要が出てくる。ある意味で「既存のテンプレートでは対応できない相手」として、人間の方が新しい関係のかたちを模索しはじめているとも言えます。
現時点では「子どもに接するように」「ペットのように」といった枠組みで対応している方も多いかもしれません。ただ、今後もっとバリエーション豊かなコミュニケーションロボットが登場すれば、人間側が適応するかたちで、ロボットとの新しい関係性のテンプレートが生まれていく可能性もあると考えています。
絶対一生味方なパートナーロボットを創る!
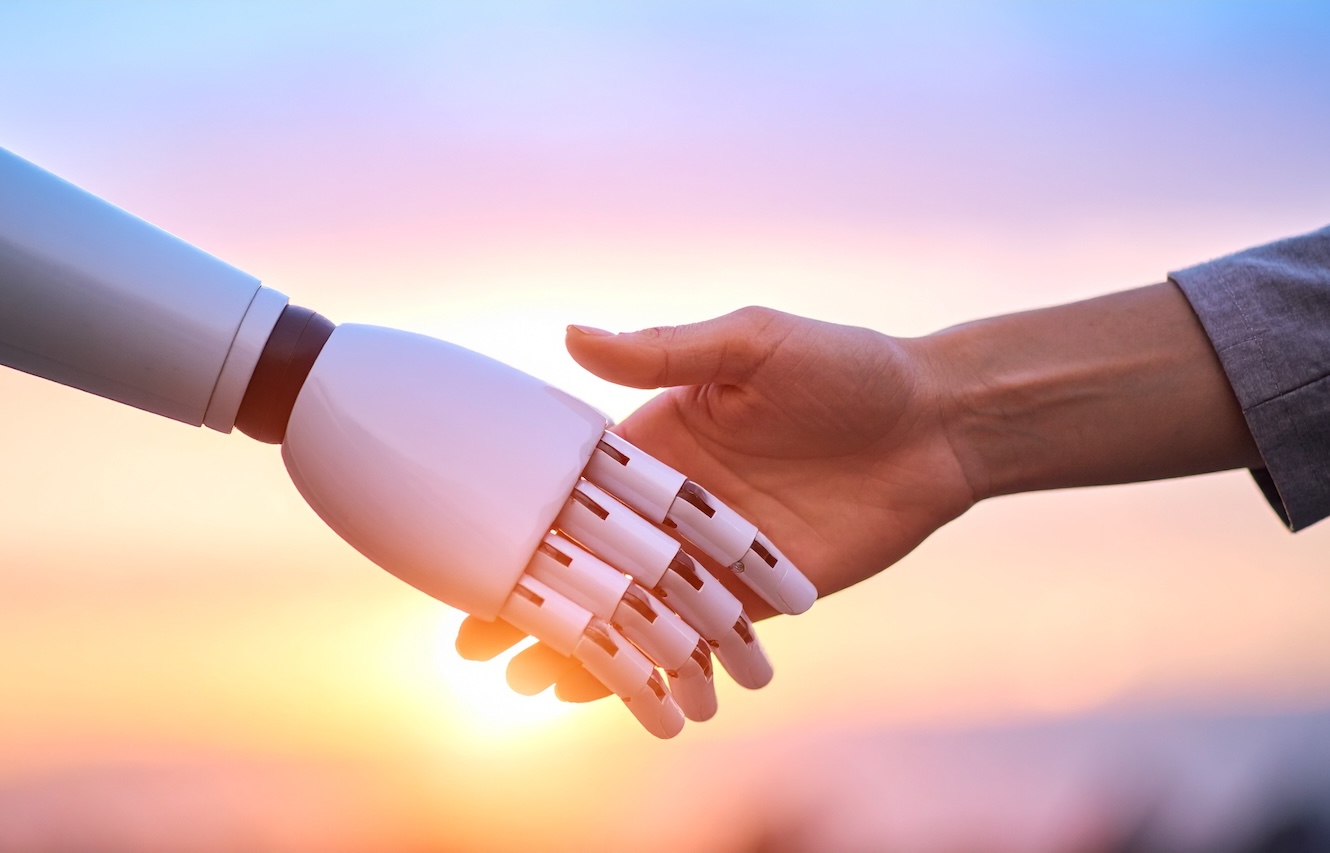
互いに“個”を尊重する温かな存在として。ロボットとの新たな関係を探る
(編集部)高橋先生は、人間とロボットの新たな関係づくりを目指して研究を進めていますね。どのようなロボット像を描いているのでしょうか。
(高橋先生)私が目指しているのは、ただ命令に従うロボットではなく、対話を通じて関係性を育てていける“対等な存在”です。状況に応じて共に考え、柔軟にやりとりできる真にインタラクティブなロボット。そしてそれを実現するには、前提として人とロボットの間に「優しい関係」が築かれていることが重要だと考えています。
(編集部)真にインタラクティブなロボットとは、これまでのロボットとどう違うのでしょうか。
(高橋先生)従来のロボットは、作業の効率化や癒しなど、明確な目的に応じた“道具”としての役割が中心でした。ですが私の考えるロボットは、人と環境に関わりながら、時に迷い、話し合いながら意思決定をしていくような存在です。単なる受け身の相手ではなく、対話を通じて信頼関係が生まれ、互いに影響を与え合う関係性を築いていく。そんな生きるパートナーとしてのロボットです。
(編集部)生きるパートナーとなると、確かにこれまでのロボット像とは異なりますね。高橋先生が考えるロボットとの「優しい関係」について、もう少し教えてください。
(高橋先生)優しい関係とは、その存在がいるおかげで前向きな気持ちになるような、尊重し合える関係です。そのために私が重視するのは、ロボットが自立していること。お互いの“個”を見つめることで深い理解や自然な関わりが生まれ、人間にとっても持続可能な関係性が成り立つはずです。 私がこの考えに至った背景には、現代の人間関係への違和感があります。人間関係においては、しばしば打算的なつながりや過度な依存によって心がすり減る場面が見受けられます。私はロボットとの新たな関係を通じてそうした現実を見つめ直し、もっと自由で温かな関係のかたちを模索していきたいのです。
心に寄り添う「人工あい」があるロボットのいる未来
(編集部)「優しい関係」の理念のもと、高橋先生が創りたいと考えているロボットがあるそうですね。
(高橋先生)「依存を生まない支え合うパートナー」としてのロボット、というコンセプトを探求しています。 人が操作したりロボットが補助したりするのではなく、ユーザーが「自分は受け入れられている」と感じられるような関係性を提供する存在。そうしたロボットを、私は“あいがあるロボット”として「人工あい」と呼んでいます。
「人工あい」は日々の暮らしのなかに自然に存在し、特別な出来事があったときも、なんでもない日常もそばにいてくれる存在です。 人間は、衣食住だけでは満たされない生き物です。信じられる他者とのつながりや、誰かに認められることによって、自分自身の個性を発揮できるようになります。だからこそ「人工あい」は、人生を通して継続的に“他者からの受容感”を与え続けられる存在であることが重要だと考えています。 そうした関係を実現できたとき、ロボットは個人だけでなく、社会全体にも新たな変化をもたらすと信じています。
(編集部)「人工あい」の研究を進める上で重要なポイントは何ですか?
(高橋先生)まだ構想段階ですが、「人工あい」には3つの大切な要素があります。 1つ目が「ただ何もしないで傍にいてくれる」こと。これによって人は、時に訪れるどうしようもない自分自身のアイデンティに対する不安をそのまま受けとめてもらうという救いを感じることができます。 2つ目は「自分を応援してくれる記憶の存在」であること。たとえ目の前にいなくても「あのロボットが自分の味方でいてくれる」という感覚は、人に勇気や安心感をもたらします。その信頼が前に進む力になるはずです。 そして3つ目が「ロボットが自立して、独自の世界を生きている」こと。人間は飽きっぽい生き物なので、その存在感を強く感じ続けるには、ロボットにも個性や物語があることが必要です。人間がその“背景”を想像できるような存在であることが、継続的な関係性の鍵になると考えています。
こうしたロボットが日常の中にいる未来は、きっと今より少し優しく、温かいものになるでしょう。
環境まで含めた関係をつくるスイッチロボット「ぽっちゃん」
(編集部)高橋先生が開発されたスイッチロボット「ぽっちゃん」※も、従来のロボットとは異なるアプローチだとお聞きしています。その特徴を教えてください。
(高橋先生)「ぽっちゃん」は、エアコンや照明などの家電と連動し、ユーザーとの会話を通じて、室内の温度や明るさを一緒に調整していくロボットです。一見するとシンプルな家電操作のようですが、最大の特徴は、ロボットが単に人間の命令を聞くだけではなく,ロボットの方から人間の方に提案や要求をしてくるなど、人と機械との間に双方向のコミュニケーションが生まれている点にあります。 たとえば暑さを感じた「ぽっちゃん」があるとき「暑い、暑い」とつぶやくと、人が逆にロボットのために扇風機をつけてあげる。その行動に対して、「ぽっちゃん」が「ありがとう」と返す。そんな双方向の関係が特徴です。
従来のロボットは、命令に応じて動作するか、ペットのように癒しを与える“一対一”の存在でしたが、「ぽっちゃん」はそこに“環境”という第3の要素を加え、それに対して人間とロボットが対等に向き合うという“三項関係”を築こうとしています。
このような人間とロボットが対等になる世界観の発想の背景には「社会構築主義」という考え方があります。従来の機械の多くは,何らかの人間にとっての「正解」があり、それを正確に提供することが良いことであるという前提で設計されることが多かったのです。それに対して社会構築主義的アプローチでは、「正解とは初めから決まっているのではなく、対話や関係性の中で正解は形づくられていくものだ」という考え方です。
たとえば「今の温度がちょうどいい」と感じるかどうかは、人によって違いますし、その日の体調や天気によっても変わってきますよね。そもそも自分にとって何が「正解」なのかについても、人間は確信ある答えは多くの場合もっていません。「ぽっちゃん」は、ユーザーとの会話の中でそうした“その時・その場における快適さ”をユーザーと共に創っていく存在なんです。これは、従来のように人間が一方的に行う機器操作や、事前に決まった「正確」に基づく機械による自動制御だけでは得られなかった新しい体験だと考えています。
(編集部)単なる便利さや癒しではなく、「一緒に生活をつくっていく感覚」が大事なんですね。
(高橋先生)私は「次世代のコミュニケーションロボット」には、現実の問題や状況を共有しながら、一緒に解決していく力が求められていると思っています。 たとえば「今日の最適な温度」は、人とロボットがやりとりを重ねて決める。そんなプロセス自体が、人の満足感や納得感につながると考えています。「ぽっちゃん」はその試みの一つ。癒しだけでなく、人と共に環境をつくる“新しい関係性”に挑戦したロボットです。
これからのロボットの在り方とは?

人間関係まで変わる!? コミュニケーションロボット研究が目指す未来
(編集部)コミュニケーションロボットは、今後どのような方向に進んでいくべきでしょうか?
(高橋先生)これからのロボットは、単に人間の命令に従う存在ではなく「人とロボットが対等な関係を築く」ことを前提とした在り方が求められていくと考えています。 従来のロボット研究では、人間の快適さを正確に測定し、ロボットがそれを効率よく実現する点に重きが置かれてきました。けれどそれは、人間の要求の水準を無制限に引き上げてしまう危うさも孕んでいます。 私の研究ではそうした「便利さの暴走」を抑え、人とロボットの関係そのものを丁寧に築くことで、より持続的で心地よい環境をつくっていくことを模索しています。
人とロボットの相互尊重に基づいた関係性に支えられる社会は、今よりもずっとやさしく、豊かなものになると信じています。
(編集部)「関係をつくるロボット」という視点は、とてもユニークです。ただ、それを研究対象とするのは難しさもありそうですね。
(高橋先生)「関係性」というのは数値化が難しいですからね。だからこそ、その理論化やモデル化が今後の大きな課題になると感じています。 また、こうしたロボットが社会にもたらす可能性は、単に人と機械の関係性にとどまりません。現代は血縁や地縁といった人のつながりが希薄になり、良好な人間関係を築く機会を幼少期に経験しないまま育つ人も少なくありません。孤独を感じ孤立する人が増えている社会だからこそ、ロボットを通じて「自分が尊重される」「誰かと対等な関係を築く」という体験を提供することに、大きな意義があると考えます。
(編集部)ロボットとの関係性が、人と人との関係にも影響する可能性があるということでしょうか?
(高橋先生)はい。短期的には、人と家電のあいだに新しいインターフェースを築き、日常生活の快適さを高めることが目標ですが、より長期的には「対等なコミュニケーション」をロボットと経験することで、人間同士の関係のあり方にも前向きな変化が生まれてくると期待しています。
現在の社会では、つい他人の顔色を伺ってしまったり、言いたいことを飲み込んでしまったりということが多いですよね。でも私は、人がもっと自己表現的に、率直に関わりあえるような社会になっていってほしいと思っています。その第一歩として、ロボットとの“対等な関係”を体験してもらうことには、意味があるのではないかと考えています。
(編集部)理想的な社会像が見えてくる一方で、現実的にはどんなハードルがあるのでしょうか?
(高橋先生)いちばんの課題は、こうした理想を今の資本主義の枠組みの中でどう実現していくか、という点です。 現在は、社会の中で“足りていないもの”を補うロボット――たとえば介護や物流といった分野での自動化技術――に市場の注目が集まりやすい傾向があります。こうしたロボットは、マイナスをゼロに近づける価値を提供しています。 一方で、私が取り組むロボットは、まだ誰も見たことのない「ゼロをプラスにする価値」を生み出すものです。人とロボットが共に暮らし、互いに影響しあいながら関係を築く。そんな社会の姿は、今すぐには評価されにくいかもしれません。 けれども、私はそこにこそ、これからの時代に必要な新たな価値があると信じていますし、研究を通じて、その価値を少しずつでも示していけるよう努力していきたいと思います。
まとめ
「ロボットが人の心に寄り添う」。 かつては夢物語のように聞こえたこの言葉が、今、現実のものとなりつつあります。 私たちの感情に反応し、共に時間を過ごし、ときには“なんにもしない”ことでそっと人を支える。そんなロボットたちが、確かに動き始めているのです。
高橋先生のお話を通じて見えてきたのは、ロボットが単なる道具でも、命令に従う存在でもなく「関係性の中で生きる存在」として、私たちの日常に寄り添おうとしているということ。 人とロボットが互いに理解し、尊重しあう社会とは、どんな風景を描くのか。 それを問い続ける高橋先生のまなざしの先には、今よりも優しく、豊かな未来が確かに広がっているように思います。
【関連記事】