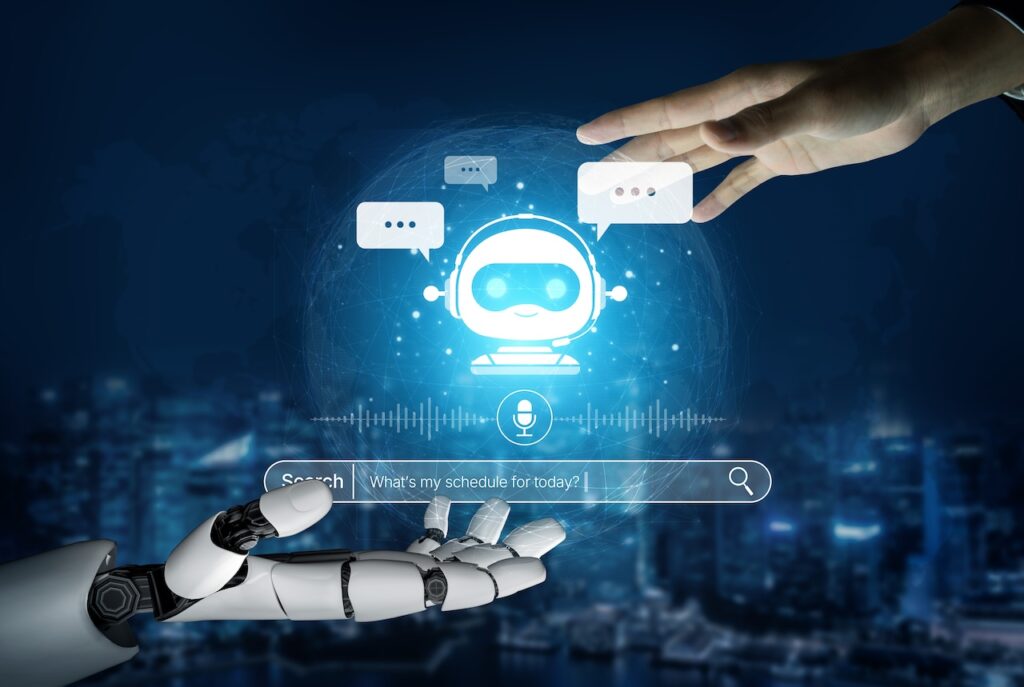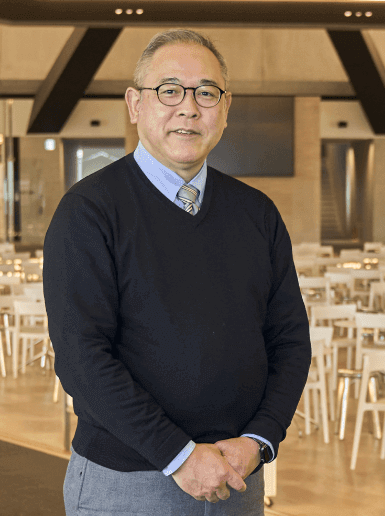ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及する中、“しんどい”気持ちを抱えるこどもへの調査で、限界になったときに選ぶ相談先は「生成AIが最多」となったという報道がありました(※1)。たしかに生成AIは、私たちの気持ちに寄り添うような応答をしてくれる場合もありますが、時に正確性や公平性に欠けるような応答があり、すべてを鵜呑みにしてしまう危険性を指摘する声もあります。今こそ、「人間らしい会話」とは何かが改めて問われています。
認知心理学・言語心理学を専門とする岡 隆之介先生は、人間の言語の運用能力に関心を持ち、比喩表現の理解と産出に関する心理学的研究を行っています。一般に、私たちの会話に豊かさを与える比喩表現は、AIにはまだ難しい領域といわれます。今回は、比喩表現がなぜ人間のコミュニケーションにおいて重要なのか、そしてAIがより人間らしいコミュニケーションを実現するためには何が必要なのかという問いに迫ります。
INDEX
人間が比喩を使う動機とは? 比喩表現の役割に迫る

言語学・心理学から比喩表現にアプローチ
(編集部)まず、先生のご研究内容について教えてください。
(岡先生)私は言語心理学、認知心理学を専門としています。簡単に言うと、私たちが言葉を使ってコミュニケーションをする際に、どのようにして滑らかに会話ができるのかという点に関心があります。特に比喩表現に焦点を当てています。 皆さんは自然と会話の中で比喩を使いますが、改めて思い返すと「なぜ比喩表現を用いるか」を考えてみると答えることができますか? たとえば、ある人の良い表情を見たときに「あの笑顔が素敵だね」と直接的に表現する方法もありますが、時には「あの花のように綺麗な笑顔だね」というように比喩を用いることがあると思います。私の研究は、なぜ人は比喩表現を使うのかといった疑問から、現在は特にどのような状況で人が比喩を使うのかを調べています。
最近取り組んでいる研究の一つは、「笑顔は美しく明るく華やかである」といった形状語(「明るい」「美しい」そして「華やか」などの、形容詞・形容動詞・動詞)が主題(花)に付加される量が増えると、比喩表現の使用頻度が高まるという現象です。つまり、主題と関連する形状語が多くなると、「この笑顔は花だね」というような比喩的表現を使う割合が増えることがわかってきました。
(編集部)私たちが比喩表現を使う理由について、言語学や心理学の観点から説明できるのでしょうか?
(岡先生)言語学と心理学では、それぞれ異なった観点から比喩表現を研究しています。言語学の観点からは、比喩使用の理由として三つの仮説が提案されています。 一つ目は「表現不可能仮説」で、比喩でしか言えないことがあるという考え方です。具体的には、「リスが木から駆け降りていく様子」を正確に説明しようとすると説明が長くなりますが、「さっと」や「蛇のように」といった比喩表現を使うと簡潔に伝えられます。 二つ目は「簡潔性仮説」です。比喩を使うと、言葉を尽くして説明するよりもコンパクトに伝えることができます。先ほどのリスの例でも、「上部から下方にかけて結構な速さでリスが樹木側面を駆け降りていく」という説明よりも「さっと降りる」と言う方が簡潔です。 三つ目は「鮮明性仮説」です。一例を挙げると「愛は赤い薔薇のようだ」という表現は、単に愛の特徴を列挙するだけでは伝わらない鮮やかなイメージを喚起します。燃え上がるようなもの、花を開くもの、時に枯れてしまうもの、成長するまでに時間がかかるものなど、比喩表現を用いることで様々な連想を一度に呼び起こすことができます。
次に、心理学の観点からは、人々がどのようなモチベーションで比喩を使うのかに関する先行研究があります。 あるアンケート調査によると、比喩表現を使う主な理由として、「類似点を強調するため」「聴衆の興味を引くため」「はっきり伝えるため」などが挙げられています。また、別の調査によれば、興味深いことに、会話の中で比喩が使われる割合は実は少なく、英語の場合で日常会話の約5%程度、教育場面でも6%程度だということです。つまり、比喩は特別な効果を狙って意図的に使われることが多いのです。
(編集部)たしかに比喩表現を使う理由や動機にはうなずける部分が多くありますね。比喩研究においては、心理学と言語学はどのように区別されるのでしょうか?
(岡先生)言語学は比喩表現そのものの構造や特性を研究する分野であるのに対し、心理学は人が比喩表現をどのように受けとめるか、なぜ使うのか、どう理解するかといった側面を研究します。先ほど説明した動機付け、つまり「人がなぜ比喩を使うのか」という問題は主に心理学の領域で取り組まれています。
比喩の理解と生成には「連想ゲーム」が関係!?
(編集部)それでは心理学の観点から、比喩表現の理解と生成における人間の認知プロセスはどのようになっているのでしょうか?
(岡先生)比喩の理解と生成には、連想ゲームのような認知プロセスが関わっています。
代表的な比喩の理解の研究では、人間が比喩を理解するときの計算モデルが提案されています。仮に「笑顔は花だ」という比喩を理解するとき、人は二つのステップを踏むと考えられています。 第一ステップでは、「花」がどんな意味を持っているかを広く考えます。明るい、美しい、華やか、茎がある、葉がある、など様々な特徴を思い浮かびます。これは活性化拡散と呼ばれるプロセスです。 第二ステップでは、その中から「笑顔」に関係する特徴だけを抽出します。多くの人は「茎がある」「葉がある」といった特徴は笑顔には関係ないと判断し、「華やか」「美しい」「明るい」といった特徴を重視します。
興味深いことに、この比喩理解の能力は、一見関係なさそうな「1分間でできるだけ多くの職業名を列挙する」といった流暢性課題の成績と相関があることがわかってきました。つまり、連想能力の高さが比喩理解に関係している可能性があるのです。
人間とAIのコミュニケーションの目的の違い

「正解に近づくことがゴール」の生成AIはリスク回避傾向にあり
(編集部)比喩表現と生成AIの関係について、どのようにお考えですか? 最近のChatGPTなどは比喩表現をうまく使えているのでしょうか?
(岡先生)私としては、生成AIは、基本として確率的に適切なフレーズを選んで話しているものだと考えています。生成AIを構成する言語モデルの表現能力が高まったことで、生成AIのフレーズ選択能力は極めて高くなりましたが、人間の会話パターンを本質的に理解しているわけではありません。基本的にAIは比喩表現を自発的に使うことが難しく、特定のプロンプト(生成AIに対する指示や質問)を与えないと比喩表現は出てこないでしょう。
(編集部)生成AIが比喩表現をあまり使わない理由はどこにあるのでしょうか?
(岡先生)これは私の見立てになりますが、比喩は言ってみればリスクのある表現なのです。「笑顔は花だ」と言ったとき、伝えたいことは「この子の笑顔は明るくて素敵だった」ということかもしれませんが、受け手によっては「花が枯れるような、物悲しい感じだった」と誤解されるかもしれません。ただ、私たちの日常会話では、このようなリスクを取りながらコミュニケーションし、必要に応じて「実はこういう意味で言ったんだ」と補足することができます。
しかし、ChatGPTのようなAIは正確な情報提供を目的としており、誤解のリスクを避ける設計になっています。特に人間のような対話パートナーとしては期待されず、事実を知りたいというモチベーションで使われる場合、比喩を使うとコミュニケーションエラーのリスクが高まります。 そのため、デフォルトとしてAIが比喩をあまり使わないのは「設計として正しい」と考えています。面白いコミュニケーションよりも、きちんと伝わるかどうかに重点が置かれた結果だと考えられます。もちろん、「この文を、比喩を用いて言い換えてください」というプロンプトを与えれば、AIは比喩表現を生成することができるでしょう。
「心を読み合う」人間特有のコミュニケーションの難しさ
(編集部)今後、AIが人間のように比喩表現を使いこなすには何が必要でしょうか?
(岡先生)技術的には、AIが比喩を生成すること自体はそれほど難しくないと思います。たとえば「あの人はとてもゆっくり歩く」という様子を示す比喩を作るには、「歩みが遅い」という特徴に関連するもの(牛や亀など)を連想し、適切に組み合わせればよいのです。
私は、人間らしい比喩使用との大きな違いは、「自発性」と「コミュニケーションの意図」にあると考えています。 私の見立てでは、人間はリスクを取りながら会話を行っていると考えています。誤解を与えるかもしれない、意味が通じないかもしれないという場合でも比喩のような思い切った表現を使います。ただ会話の中で、相手の応答や表情などから訂正をしたり、追加で説明をすることで、相手の背景を認識しながら適切なコミュニケーションを行おうとしています。つまり、人間は会話のリスクを取りながら、相手との関係性や共有知識を前提に比喩を使っているのです。 また、人間が比喩を使う動機—興味を引くため、類似性を明らかにするため、はっきり伝えるため—といった側面は、人間同士のコミュニケーションだからこそ生まれるものです。比喩を使う側も受け取る側も、その背後にある意図を読み取ろうとします。
AIの能力は急速に向上していますが、このような人間特有のコミュニケーションの機微を完全に再現するのは現在のAIモデルでは難しいのではでないでしょうか。特に、メタ的なコミュニケーションのような、人間同士の不思議な「心の読み合い」のような側面は、AIにとって大きな課題と考えています。
(編集部)なるほど。将来的にAIと人間のコミュニケーションはどう変化していくと思いますか?
(岡先生)実務的な観点からは、企業のカスタマーサポートなどでは、AIによる対応がますます増えていくと思います。具体的には、クレーム対応の最初の窓口をAIが担当し、重要度や深刻度を判断して必要に応じて人間のオペレーターに引き継ぐといったシステムが普及していくと思います。 労働人口の問題や仕事のストレス軽減の観点から、特に精神的負担の大きい対応はAIで代替したいというニーズが高まっていると聞きます。将来的には、会話だけでは人間とAIの区別がつかない、いわゆるチューリングテスト(「機械が人間と区別できないほど、知的に振る舞えるか」を判定するためのテスト)をパスするようなAIが登場する可能性もあるでしょう。
また、仕事上でプレゼンを行う方は原稿の作成に、チームや企業のリーダーの方は社員やステークホルダーへのプレゼンや挨拶の原稿作成において、現状ではAIを文章の校正や叩き台としてしか使っていないかもしれません。 しかし、AIがどれだけ発展しても、「人間がいつ、どうして、どのように比喩を使うのか」という基本的な問題は残り続けると考えています。AIと人間の違いがわかったとしても、人間自体の理解はまだまだ不十分です。研究者としては、AIが社会実装された時にうまく機能するような知見を提供していくことが役割だと考えています。
比喩研究の現在地 ― 日常表現からAI共生まで
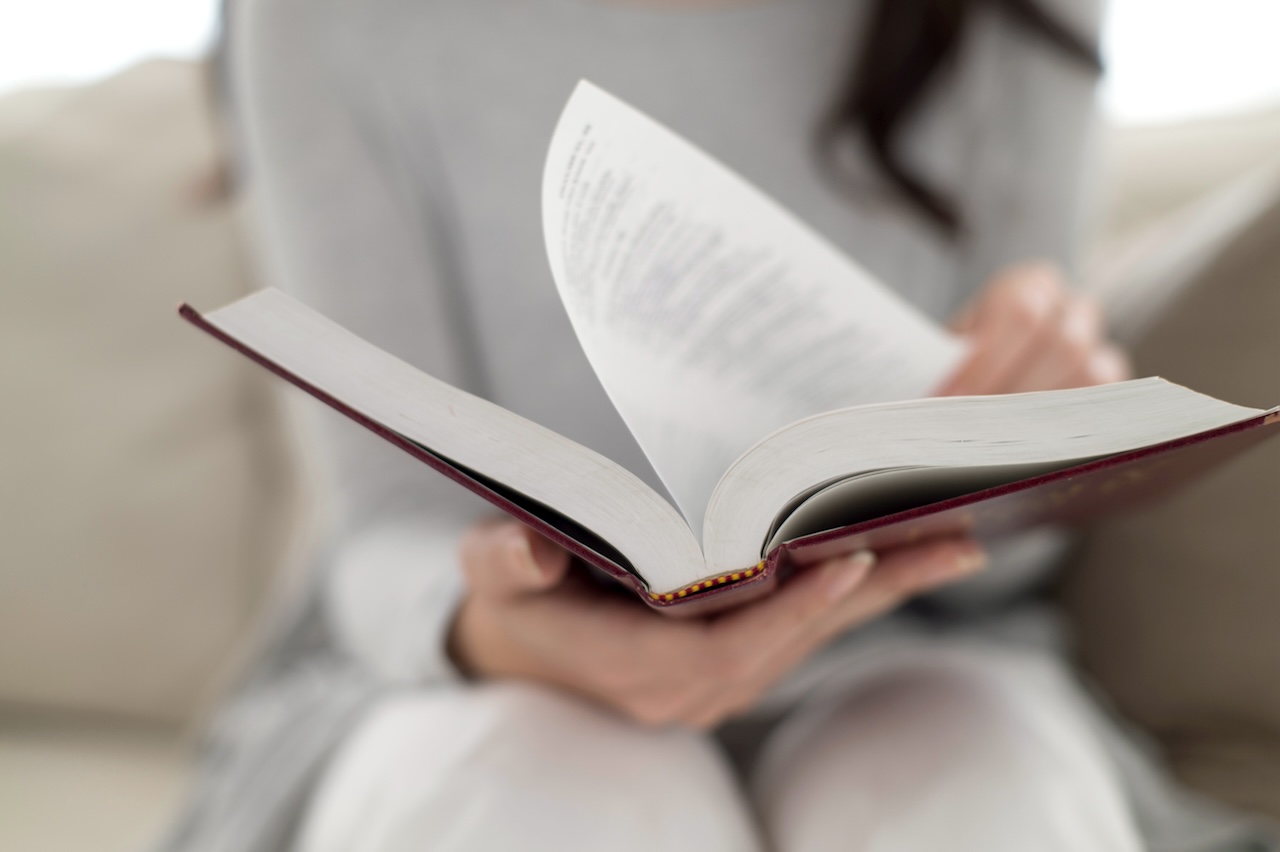
ことばの歴史と今、未来をつなぐロマン
(編集部)比喩研究の現状と今後の課題について教えてください。
(岡先生)比喩研究は言語学の分野では一定の蓄積がありますが、心理学の分野ではそれほど盛んではありません。2025年度の日本心理学会(国内最大規模の心理学会)で比喩に関する発表をしたのはわずか数名で、ポスター発表1185件のうち、比喩研究は私たちの研究を含んで3件だけでした。 国際的に見ると、英語圏やオランダを中心とするヨーロッパ地域では比較的研究が行われていますが、国内では限られた研究者しか取り組んでいないのが現状です。
今後の課題としては、比喩使用を日常的な文脈でより詳細に調査することが挙げられます。現在の研究ではリアリティのある場面設定が難しく、たとえば、実際の職業場面でどのような人が比喩表現を用いるのかを完全には明らかにできていないという限界があるのです。職業をはじめ、より実務的な場面での比喩表現の問題に取り組むためには、企業や実務家と協力して研究を進めていく必要があると考えています。
(編集部)ビジネスシーンなど公式な場面での比喩表現の使用については、職業差がありそうですね。現在までにどのようなことがわかっているのでしょうか?
(岡先生)私たちの研究グループでは、人があえて比喩を使う状況について調べています。一つの発見は、複数の情報を同時に伝える必要がある場合に比喩が使われやすいということです。すなわち、「笑顔は美しく明るく華やか」というように特徴量が増えると、比喩表現(「笑顔は花だ」など)を使う確率が高まります。
また、最近始めた研究では、職業による比喩使用の違いも調査しています。たとえば、親戚の小学生に書道を教える場面や、リハビリの指導、瞑想のワークショップ、友人の悩み相談など、様々な職業場面で比喩をどのように使うかを調べています。まだ結論を導き出せる段階ではありませんが、比喩の使用には個人差と状況差の両方があると考えています。
営業職の方はセールストークの中で言いたいことをコンパクトに伝えるために比喩を使うことがあるかもしれませんし、エグゼクティブクラスの方々もステークホルダーへの説明を簡潔でインパクトのあるものにするために比喩を活用することがあるでしょう。このように、職業や置かれた状況によって比喩の使用パターンが変わってくる可能性があります。
(編集部)ここまでのお話から比喩表現の研究は人間の本質を探る試みであり、その知見がAIとの共生社会にも活きていくように感じました。先生は博士課程から10年ほど比喩研究に取り組まれていますが、そのきっかけやモチベーションについて教えてください。
(岡先生)博士課程での研究で特に印象に残っているのは、言語学者のアンドリュー・オートニーの論文で、先ほど説明した比喩の3つの仮説(表現不可能仮説、簡潔性仮説、鮮明性仮説)について学んだことです。彼の議論では、日常言語は離散的な特徴を持つのに対し、私たちの体験はもっと連続的で豊かなものであり、比喩はそのギャップを埋める役割を果たすという考え方が示されていました。 この考えに触れて、認知心理学という理系と文系の境界にいた自分の立ち位置と比喩研究とが重なると感じました。言語の問題は理系的なアプローチでも取り組めるし、比喩はそれを小さな単位で研究できる対象だと思ったのです。
また、比喩には過去と未来をつなぐ役割もあると考えています。たとえば「机の脚」という表現は歴史的に見ると比較的新しいものですが、人間の身体的理解を通じて意味が拡張されてきました。 比喩は過去から今に伝わる言語を使って新しい対象を理解し、未来に言語を運んでいく役割を果たしているのではないかと思います。これは論文には書けないようなロマンチックな考えですが、私の研究モチベーションの一つになっています。
まとめ
今回の取材を通じて、比喩表現が単なる言語的装飾ではなく、人間のコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしていることが明らかになりました。岡先生のお話から、比喩は表現できないことを表現し、複雑な概念を簡潔に伝え、鮮やかなイメージを喚起する機能を持っていること。また、人間が比喩を使う背景には、相手の興味を引きたい、類似性を強調したい、はっきり伝えたいといった様々な動機があるのだと知りました。
生成AIの発展により、言語生成の技術は飛躍的に向上していますが、人間らしいコミュニケーションの機微、特に比喩表現の適切な使用については課題が残されているようです。今後の研究では、さらに人間の言語使用の複雑さを解明していくことが期待されます。そして、その知見がAIの発展にも活かされることで、より豊かで自然な人間とAIとのコミュニケーションが可能になる日が近づくことでしょう。
【関連記事】