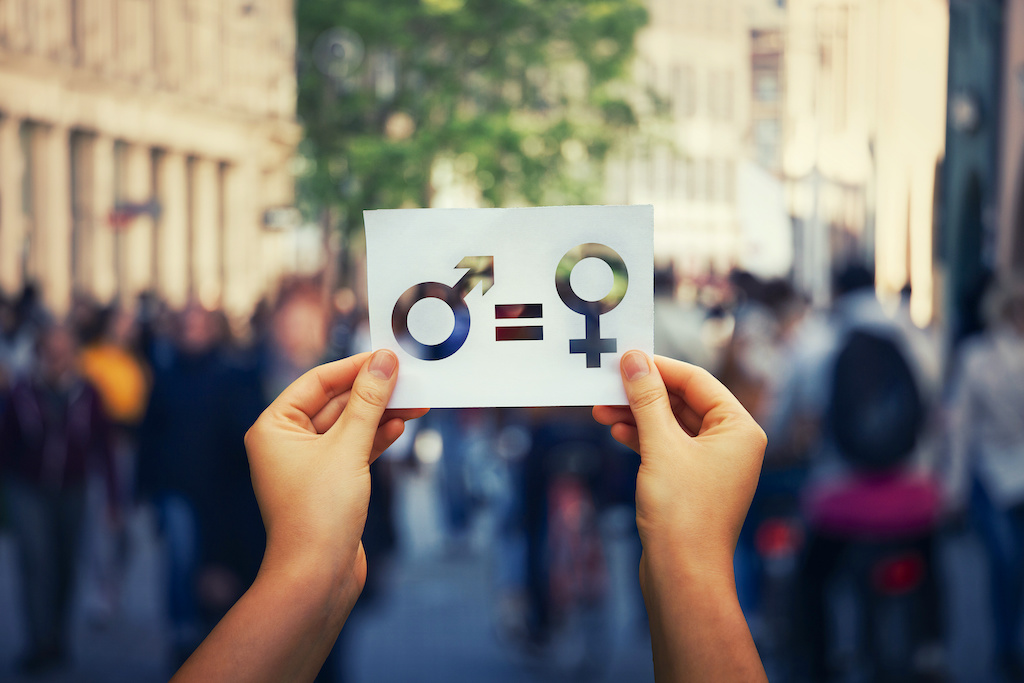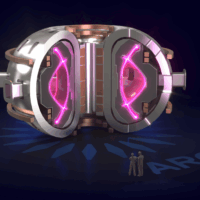5月のG7広島サミットと合わせて注目されたLGBT理解増進法案(LGBT法案)。LGBTQ+など性的マイノリティへの理解増進を目的とした議員立法で6月16日に成立しましたが、一部表現を巡って議論が紛糾する場面もみられました。 近年は働き方やライフスタイル、家族の在り方など、さまざまな点で「多様性」が注目されるようになり、個人の生き方についても、多様性を尊重しようとする働きかけが進んできました。とくに6月は「プライド月間(Pride Month)」と呼ばれ、世界各地でLGBTQ+の人権を啓発するための活動も行われました。
LGBTQ+の人権について関心が高まるたびに、さまざまな議論が巻き起こる一方で、私たちはどれほどその歴史や背景について知っているでしょうか?またLGBTQ+と性的マイノリティを一括りにして議論することも重要ですが、それぞれの違いや社会的位置づけをどれほど理解しているでしょうか?
今回はLGBTQ+の中でも「L:レズビアン」にかかわりがある女性同士の親密な関係に焦点をあて、社会学から研究を進めている社会学部の赤枝香奈子教授と、日本におけるLGBTQ+の歴史と日本社会のとらえ方の変遷を客観的に紐解きます。
INDEX
理解を深めるには変遷を知るべし

プライド月間には由来と歴史がある
(編集部)6月は「プライド月間(Pride Month)」でしたね。
(赤枝先生)街中でもレインボー・フラッグを目にする機会が増えました。6月が「プライド月間」とされている理由を知っていますか? 背景には1969年6月にアメリカ・ニューヨークで起きた「ストーンウォールの反乱」と呼ばれる歴史的な出来事があります。当時のアメリカでは多くの州で同性愛を犯罪と定めており、性的マイノリティへの嫌がらせや暴力も日常茶飯事でした。そんな中、ニューヨークにある「ストーンウォール・イン」というゲイバーに警察の手入れが入ります。そのこと自体は、当時よくあることだったのですが、この時は店内にいた客たちは警察に抵抗し、さらに多くの性的マイノリティが集まってきて、自分たちに対する不当な扱いにNOの声を上げ、大規模な抗議運動へと発展したのです。 この出来事は当事者による社会運動が盛り上がる大きなきっかけとなり、翌年6月にはニューヨークで初のプライドパレードが開催されました。
(編集部)その流れを汲んで、毎年6月がプライド月間とされているんですね。
(赤枝先生)今の若い世代の人々は当たり前のようにLGBTQ+への理解があるようで、すばらしいと感じます。しかし、LGBTQ+に関わる問題を社会課題として扱うには、その歴史を知らずして深い議論はできないのではないでしょうか。LGBTQ+の問題は、当事者にとっては自分たちに向けられる差別や偏見、ステレオタイプ化した見方をし、人権を否定する社会との闘いである一方、当事者以外の視点から見ると、これまでたびたび社会にとっての目新しいコンテンツ、ブームとして消費されてきた側面があります。 まずベースとして共有しておきたいのが、同性同士の性的関係は、歴史上、いつでもどこにでも存在したということ。その上で、時代や社会によって世間の評価や見られ方は変化するということです。
近代以前:今でいう「同性愛」は特別な話題ではなかった?
ザ・男性社会だった昔の日本。男色/女色が並び話されていた
(編集部)歴史的な変遷から考えたいと思います。
(赤枝先生)私が研究をしているのは主に近代以降の女性同士の親密な関係です。それ以前、江戸時代の大奥や遊廓など女性しかいない環境下で女性同士の性的関係が見られたようなのですが、史料としてほとんど残っていないため詳しくは分からないのが現状です。ただ、春画などでそういった描写が見受けられます。
一方で男性同士の性的関係は、武士や僧侶の間で、また歌舞伎の世界などでしばしば見られたことを示す記録が数多くあります。男性同士で関係を持つことを示す「男色(なんしょく)」に対して、男性が女性と関係を持つことを「女色(にょしょく)」と言いますが、当時の日本では男色と女色のどちらが好ましいかというような議論もありました。男色は宗教的にも道徳的にも罰せられる対象ではありませんでした。昔は女性の社会的地位が低かったこともあり、むしろ男性同士の関係の方が尊いものであるという考えもありました。
(編集部)当時のジェンダー規範などにも関係してくるんですね。
(赤枝先生)そもそも近代以前には「同性愛」や「同性愛者」という言葉や概念はありませんでした。同性同士の性愛が人を分ける指標にはなっておらず、人格とは切り離して捉えられていました。男性同士の関係についても、「ただそういう行為がある」といった認識だったことがうかがえます。
キリスト教社会では同性同士の関係は処罰の対象に
(編集部)日本では宗教的にも道徳的にも罰せられることはなかったということですが。
(赤枝先生)西洋キリスト教社会では、昔から同性同士の性的関係は宗教上の罪でした。さらに19世紀後半ごろからは、ドイツやイギリスで刑法で罰せられる対象とされていきます。それに対して、同時期に西洋で誕生した性科学(人間の性を科学的に研究する学問)からは、「同性間で性行為を行う人は、犯罪者ではなく病人なのだ(だから罰するべきではない)」と擁護する動きが出ました。この言説はある程度、同性愛の擁護に作用したと考えられますが……。 セクシュアリティが人を分ける指標として明文化されたことで、そういう行為をする人たちが「普通とは違う存在」「同性愛者は異常な存在」と認識されることにも繋がりました。
明治~大正:同性愛は異常? 性科学の輸入がもたらした影響

新しい学問が庶民の感覚に変化をもたらした
(編集部)西洋で誕生した性科学は日本にどういった変化をもたらしたんですか?
(赤枝先生)19世紀末ごろから日本に性科学の考え方が輸入されました。ただ、性科学は専門的な学問と言うよりは、わかりやすく解釈され、世俗的な受けとめ方をされたようです。性科学の知識がおもしろおかしく庶民に広まり、結果「同性愛は‘変態性欲’である」という認識が徐々に浸透していきました。キリスト教の教えをバックボーンとして持たない日本社会では、先ほどの擁護のニュアンスは消え、「異常なんだ」「普通とは違う人たちなんだ」という部分だけ一人歩きして、差別を生み出すことになりました。 ちなみに、「同性愛」という言葉が使われるようになったのは1910年代以降のことです。
女性同士の親密な関係に対する、社会の横暴なカテゴライズ
(編集部)赤枝先生は、明治・大正時代の女学生の間で広まっていた「エス」という関係性についても研究されていますね。
(赤枝先生)明治半ばから大正時代にかけて女学校に行く女性たちが増え、その中で「おねえさま」「○○ちゃん」と呼び合い、親密な関係を築く女学生たちが見られるようになりました。そのような関係の呼び方は学校ごとに違っていたりもしたようですが、広く使われるようになったのが、sisterの頭文字をとった「エス」という呼び方です。ただ、エスのような関係性は当初、一般に広く知られるものではありませんでした。 それが注目を集めたのは1911年、女学校の卒業生2人による心中事件が起きた時からです。当時の新聞で「恐るべき同性の愛」などとセンセーショナルに報道され、女学生間の親密な関係性が広く知られるようになりました。とは言っても、女性同士の親密な関係性には、心中事件に結びつくような永続的で深刻な関係と、そうではない穏やかで“健全な”関係の2種類があるというような受けとめ方をされていました。前者は「真の同性愛」、後者は「仮の同性愛」などと呼ばれていたんですよ。
(編集部)「仮の同性愛」というものがあるんですか?
(赤枝先生)エスのような関係性は女学生時代だけの一時的なもので、やがて‘卒業’してしまうものだから心配する必要はないと捉えられたんです。 これはセクシュアリティの問題だけでなく、当時のジェンダー規範が絡んでいるといえるでしょう。というのも、戦前は中等教育以上は男女別学で、男女交際の方が危険視されていました。一方で、女学校に行くような階層の女性は、女学校卒業後は結婚し家庭に入って家事や育児をすることが当然とされ、夫や子どもとの間に愛情に満ちた関係を築くことが期待されていました。となると、他人と愛情関係を築ける女性であることが大切で、女学生時代のエスの関係はやがて異性愛に至る成長の一段階として位置付けられたのです。
(編集部)いずれは本当の愛情(異性愛)に目覚めるだろうという意味での「仮」なんですね。それは当事者たちの思いを無視した、偏見に満ちた押さえつけですね。
(赤枝先生)すべての人間は異性を愛するものだという「異性愛規範」の考えが「当たり前で正しい」とされていた時代、社会がつくった「女性はこうあるべき」という役割に押し込める形で女性同士の親密な関係を抑圧していたんですね。 加えて、日本は昔からジェンダー規範とセクシュアリティ規範が強く絡みあっており、女性が性の主体になることに対して否定的な風潮があります。女学生同士の親密な関係についても、あえて「仮の、穏やかなもの」と決めつけることで、女性が性の主体となること(セクシュアリティの問題)として顕在化させなかった。これは男性の同性愛にはあまり見られないような、つまり女性の同性愛に特有の差別の形と言えるでしょう。
昭和:同性愛への偏見、当事者たちの働きかけ。価値観の転換が訪れる

1950年代、アメリカの「キンゼイ報告」がもたらした衝撃
(編集部)時代を戦後日本に移したいと思います。
(赤枝先生)1950年代、世界に衝撃をもたらしたのが、アメリカの性科学者アルフレッド・キンゼイ博士によって発表された「キンゼイ報告」です。全米の男女約18,000名を対象に実施された、性行動に関する調査報告書でした。この報告書は日本にも多大な影響を与え、同性愛に対する価値観にパラダイム転換を引き起こしたのです。 それまでの日本では、同性愛といえば女学生間に見られるような、精神的に親密な関係だとの認識が広まっていました。 しかしキンゼイ報告によると、実際は男性同士の方が多く、さらに同性愛は性的接触を伴う関係が多分に存在するという調査結果が出されます。日本における同性愛の概念を覆しました。
(編集部)これまで実態が知られていないゆえに社会の中で勝手に枠組みされていたものが覆った。それだけ大きな社会的インパクトだったんですね。
(赤枝先生)同時に1950年代は性をテーマとした雑誌が出され、誌面で同性愛が取り上げられたり、またゲイボーイが接客するゲイバーがオープンし、注目を集めるなど、一種のゲイブームが起きました。さらに、女性間の性的な関係を指す言葉として「レスビアン」という語が用いられ始めたのもこの頃。キンゼイ報告でも使用されていたことで、日本社会に浸透していきます。1960年代初めにはレズビアンが一般雑誌でも取り上げられるようになり、とりわけレズビアン・バーやそこで働く男装の女性が新しい存在として注目を集めることになります。
1960~1970年代、過激な性描写の商業化とメディアによる偏見の増幅
(編集部)その後はどのような形で取り上げられたのでしょうか。
(赤枝先生)1960年代は経済発展や雑誌メディアの発達に伴い、性に関する情報が世の中に溢れはじめた頃です。マスメディアを通じて「異常な性的嗜好の一つとしてのレズビアン」という認識が広まっていきます。アダルトコンテンツは商業化されるに伴って、描写や内容は争うように過激さを増し、そんな中で女性同士の親密な関係もポルノ化され、異性愛男性にとっての消費の対象となっていきました。週刊誌がレズビアンをテーマに過激な記事を載せたり、1970年代になるとポルノ映画でレズビアン作品が人気を集めたり……。非常に偏った形でレズビアン・イメージが浸透してしまったのです。
(赤枝先生)当時を経験した当事者たちの多くは、メディアに登場するレズビアンをとてもネガティブに捉えていたようです。1970年代には、女性解放運動に触発された一部の女性たちが、そのような世間のレズビアン像を否定し、「女性を愛する女性」としてのレズビアンの生き方や生活のあり方を模索する活動を開始しました。 それでも、当時はレズビアンであることが大きなイメージダウンとなる世の中だったと言えるでしょう。1980年には、著名な女性芸能人が同性の元パートナーによって2人の関係性をアウティング(暴露)される事件が起きました。当時のメディアが「この人はレズビアンだ」とセンセーショナルに報じ、結果としてその人は芸能界を引退することになったことからも想像できます。 現代でも自身がレズビアンだと公表する人は、ゲイやトランスジェンダーなど他の性的マイノリティの人たちに比べて圧倒的に少ない印象がありますが、これは1960年代から続くレズビアンへの偏見の根強さ、さらにはそれ以前からの、女性の性的主体性を認めないジェンダー規範と関係があると思われます。
平成:偏見との闘い。可視化され始めた当事者たちの苦しみ

1980~1990年代、差別解消に向け団結・行動するLGBTQ+当事者たち
(赤枝先生)1980年代から1990年代にかけてはエイズ禍の時代です。ホモフォビア(同性愛嫌悪)が顕在化し、HIV感染への不安も高まる中、同性愛者たちのコミュニティの中から、差別に異議申し立てしたり、お互いに情報交換やサポートをしたりするための活動団体が生まれます。自らの存在を可視化させ、排除や偏見に対して異議を唱える。好奇な視線に晒されがちだった当事者たちをめぐる状況は、1990年頃に転換期を迎えたと言えるでしょう。
そして1990年代には、東京都が運営する「府中青年の家」で同性愛者グループが利用上の差別を受けたことを不当であるとして裁判を起こします。1997年の東京高裁の判決では、同性愛者の権利、利益を擁護することが行政の責務とされ、原告側は勝訴しました。
(編集部)大きな転換ですね。
(赤枝先生)画期的な判決だったと言えます。同時期には活動団体の働きかけによって精神医学、心理学の領域で異性愛規範の見直しが進み「同性愛は性的逸脱ではない」といった発表がなされました。 当時はこれらが基盤となり、日本でも性的マイノリティに対する社会的課題解決への道筋が拓けるかと期待されたんですが……。その展開を鈍化させたのが、1990年代後半から日本に巻き起こったジェンダーバックラッシュです。社会の中で男女共同参画の取り組みに対する反発が大きくなり、日本のジェンダー政策は停滞しました。その煽りを受けて、性同一性障害をめぐる取り組みを除き、性的マイノリティに関わる課題も置き去りにされてしまったと考えられます。 それが再び大きく動いたのは、2010年代でした。
2010年代、出発点はマーケティング? 今に続くLGBTQ+ムーブメント
(編集部)なぜ2010年代だったんでしょう?
(赤枝先生)2010年代の動きはそれまでと明らかに違いました。従来のLGBTQ+の社会運動は、当事者たちがそれぞれ集まってミニコミを作ったり、自分たちが読むための雑誌を出したり、あるいは差別をなくすために地道な草の根的運動を展開していました。対して2010年代を境に始まったLGBTQ+ブームともいえる動きは、それまでの運動とは切り離された形で、突如として大々的に始まった印象です。自分たちのコミュニティに向けて、というよりはその外部に向けた活動が中心で、大企業を巻き込んだ取り組みが目立つ、ビジネスに親和的な動きでもありました。
個人的には、東京五輪誘致を見据えて大手広告代理店が仕掛けた経済的なキャンペーンの側面もあったと考えています。それは2010年に日本初のLGBTQ+アワードである「Tokyo Superstar Awards」が創設され華やかな受賞パーティーが開かれたことや、2011年に一般男性誌で、2012年には複数の経済誌で「LGBT市場」なる言葉が使われ、性的マイノリティを新たな消費者層として捉えるような特集が組まれたことからも推測できます。大手広告代理店は独自の調査をもとにLGBTQ+の数を算出し、未開拓の市場として企業にアピールしました。少し後のことになりますが、2017年にはLGBTQ+の活動家が「マーケット(市場)が人権を作る」といった趣旨の発言をしたことが問題になったりもしました。「LGBT市場」への注目をきっかけとしてLGBTQ+への関心が高まり、ブームを作り出しました。
(編集部)きっかけがマーケティングというのは引っかかる部分もありますが、多くの人がLGBTQ+を認識し、考える流れになったことは歓迎できるような気がします。
(赤枝先生)たしかに、2010年代のLGBTQ+啓発活動は一定の成果を挙げたと思います。メディアをうまく使いながら、社会に向けて広く発信したことで、「アライ」と呼ばれる人たちを多数生み出しました。アライ(ally)とは、自らはLGBTQ+ではないものの当事者たちに連帯し、その活動を支持する人々を指します。多くのアライを生み出し、巻き込んだことが、2010年代の運動の特徴といえます。 ムーブメントは社会的注目を集め、2015年には東京都渋谷区が日本で初めて同性同士のパートナーシップを認める条例を可決。以後、地方自治体でパートナーシップ制度が導入されるようになりました。
ただ、私自身も含め、2010年代当初は「キラキラ系」とも称された華やかなムーブメントに違和感を抱いていた人も少なからずいたと思います。その後、時間が経つにつれ、長年、活動してきた人たちと2010年代以降に新しく活動に関わるようになった人たちが徐々に融合してきている印象です。
(編集部)LGBTQ+に対する社会課題の共有が全国的なものとなったんですね。
(赤枝先生)「ブーム」の中で華やかに見えたのは実はうわべだけで、現状としては必ずしも当事者が生きやすい社会ではないことを突きつけるような出来事が起きました。2016年に報道された「一橋大学アウティング事件」です。その前年、一橋大学の法科大学院に通っていた男性が友人間のLINEグループでゲイであるとアウティングされたことをきっかけとして自死していたことが報道され、当事者や活動団体に大きな衝撃を与えました。
そのような事件には至らないまでも、性的マイノリティのいじめや不登校の経験率、希死念慮の割合は高いです。また世界的に見れば、2001年にオランダで同性同士のカップルも男女のカップルと同じ結婚制度が利用できるようになり、現在ではそのような同性同士の婚姻(同性婚)を認めている国が30カ国以上ありますが、日本では現在でも全国的なパートナーシップ制度も同性婚の制度もありません。 2019年には全国5カ所(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)で同性同士の婚姻を認めるよう、国を相手取った訴訟がスタートしました。 こういったニュースは、性的マイノリティに対する根強い差別や当事者の生きづらさが改めて認識される機会になっていると思います。
(編集部)「同性婚訴訟」と呼ばれている各地裁での裁判は、ちょうど先月、すべての判決が出揃いましたね。(※参考)
(赤枝先生)同性婚を認めていない法律上の規定を合憲と判断したのは大阪地裁のみで、札幌と名古屋が「違憲」、東京と福岡は「違憲状態」と判断しました。個人的には画期的な判決になったと受けとめており、この先の展開に注目しています。
令和:真の多様性とは何か? 人権を歴史から考える大切さ

一過性のブームで終わるか根付くのか、今が分岐点
(編集部)今、日本社会は少子高齢化、成熟化を迎え、政治や経済などあらゆる場面でイノベーションが求められています。そのカギとしてダイバーシティが注目され、性的マイノリティへの理解も広まりつつあります。日本におけるLGBTQ+喫緊の課題とは何でしょうか?
(赤枝先生)LGBTQ+への理解と課題解決が、人権に関わる問題として根付いていくかどうかだと考えます。 冒頭でもお話ししたとおり、性的マイノリティの話題はこれまでの歴史の中でたびたびブームとして消費されてきました。2010年代から続いてきた流れも、すでに持続的なものにはなりつつありますが、より社会に根付いたものにしていくためには、今が大事な分岐点だと思います。ブームによって呼び起こされた関心は、離れていくのも早いと考えられるからです。
(編集部)すべての人にとっての「自分ごと」として根付くためには何が必要でしょうか?
(赤枝先生)同じ時代、社会を生きているという意味では、全員が当事者であると言えます。その上で、性的マイノリティを取り巻く環境の何が変わって、何が変わっていないか、それはなぜなのかという観点から議論が展開されていくことが必要でしょう。 あるアンケートによると、今の20代の大多数が同性婚について賛成であるという調査結果が出ています。私自身、学生から「なぜ同性婚が認められないのか?」といった質問を受けることもしばしばです。その感覚に時代の変化を感じる一方、もしもそのような感覚が時代の空気感で何となく身についただけのものならとても心許なく、議論も浅いものになってしまうのではと懸念しています。 「なぜ、LGBTQ+の人々は今も社会で不自由な思いをしているのか」ということを、この社会が抱える問題として捉え、歴史や社会的価値観の変化を踏まえながら、政治的動きにも関心を抱くことが、本来の意味でのLGBTQ+など性的マイノリティとの相互理解、ダイバーシティの促進につながると考えます。
まとめ
今回はLGBTQ+の中でも女性同士の親密な関係に焦点をあてながら、日本社会における性的マイノリティに対する価値観の変遷、メディアの影響、当事者たちの活動などを見てきました。 性教育をはじめ、日本人はとかく性的なものについて教育的・社会的な観点からの議論をタブー視しがちです。一方で、アダルト産業としての商業的観点からは奔放に扱ってしまう傾向があるように思います。 人々の間でジェンダー観やセクシュアリティ観が更新され続ける中、真のダイバーシティを実現する基盤となるのは、社会課題に対する歴史的経緯と価値観の変遷を理解し、深い議論を展開する姿勢であると感じました。
【関連記事】